令和7年10月 栄養教室
10月は「地場産物と栄養」をテーマに開催しました!
村で生産される食材には、長いも、ごぼう、大根、にんじん、スルメイカ、鮭、ウニ、アワビ、昆布などがあります。
地元で生産された食材を地元で消費する「地産地消」に取り組むことで、新鮮な食材が手に入り、地元の産業を支え、環境の保護や地域の活性化につながります。また、地元の食文化への理解が深まり、健康的で楽しい食生活にもつながります。地産地消を心がけ、美味しく食べながら楽しい食生活を送りましょう。
村で生産される食材と栄養
- 長いも:食物繊維と難消化性デンプン(体内で消化できないデンプン)である「レジスタントスターチ」が多く含まれており、これらはほとんど消化されないまま大腸まで届いて腸内環境を改善する働きがあるため、便秘の解消に効果的。また、食事の消化吸収をゆるやかにする働きもあるため、食後血糖値の急激な上昇を抑える効果も期待できる。
- ごぼう:水溶性食物繊維と不溶性食物繊維のどちらも豊富に含んでいる。水溶性食物繊維は食後の血糖値上昇をゆるやかにしたり、余分なコレステロールや塩分を外に排出する働きがある。不溶性食物繊維は排便をスムーズにする働きがあり、便秘の解消に効果的。また、皮はポリフェノールの一種である「クロロゲン酸」が豊富。抗酸化作用をもち、細胞の老化を防止する効果が期待できる。
- 大根:根の部分には、ストレスや風邪に対する抵抗力を高めるビタミンCや血圧を下げる効果のあるカリウム、胃もたれを防ぐ消化酵素などが多く含まれている。葉の部分には、主にビタミンCや目の粘膜を正常に保つビタミンA、丈夫な骨を作るために欠かせないビタミンKが含まれている。
- にんじん:緑黄色野菜の中でもβカロテンの多さはトップクラス。皮膚や粘膜を丈夫にするため、免疫力を高めることに役立つ。抗酸化作用が強く、肌の老化防止にも効果的。皮の近くに多く含まれるため、皮ごと食べるか、皮を薄くむいて食べるのがオススメ。高血圧予防に役立つカリウムも豊富に含まれている。
- スルメイカ:たんぱく質の宝庫であり、筋肉の成長や修復に役立つ。また、抗酸化作用をもつビタミンEが含まれており、細胞の老化防止や血行改善などの働きが期待できる。その他、体内でコレステロールを下げる作用があるタウリンも豊富に含まれている。一方、痛風を引き起こす原因となるプリン体を豊富に含むため、食べすぎに注意。
- 鮭:赤い色素成分である「アスタキサンチン」を豊富に含み、強い抗酸化作用があるため、肌の老化防止や眼精疲労の改善、筋肉の疲労回復に効果的。DHAやEPAも豊富で、血液中の中性脂肪やコレステロールを低下させ、高血圧の予防・改善に役立つ。
- ウニ:カリウムが多く含まれており、体内の塩分(ナトリウム)を排出し、血圧を下げる作用がある。その他、βカロテンを多く含むため、視力の維持や免疫機能の維持に役立つ。一方、動脈硬化や脂質異常症などを引き起こす原因となるコレステロールや、痛風を引き起こす原因となるプリン体を多く含むため、食べすぎに注意。
- アワビ:たんぱく質が豊富な食材であり、皮膚や血管、骨、軟骨などを丈夫に保つ働きがあるコラーゲンを豊富に含む。その他、骨の形成や筋肉の収縮に必要なマグネシウムが多く含まれている。血液を作る鉄分も豊富に含まれており、貧血予防に役立つ。
- 昆布:ねばり成分は「アルギン酸」や「フコイダン」といった海藻特有の水溶性食物繊維であり、糖質や脂質の吸収を抑えてコレステロール値の上昇を抑える働きがある。その他、カルシウム、鉄、カリウム、ナトリウム、ヨウ素などのミネラルが豊富に含まれている。また、旨味成分である「グルタミン酸」を活かすことで、他の調味料の使用量を減らし、おいしく減塩することができる。
栄養教室の様子


★10月メニュー★
- ごぼうと豚ひき肉の混ぜごはん
- 鮭とまいたけの味噌マヨ焼き
- 桜えびのにんじんしりしり
- 長いもとわかめのさっぱりサラダ
- ブルーベリージャム入りヨーグルト
材料や作り方はこちらをご覧ください。
![]() 令和7年10月 栄養教室メニュー .pdf [ 369 KB pdfファイル]
令和7年10月 栄養教室メニュー .pdf [ 369 KB pdfファイル]
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2025年11月6日 /
更新日: 2025年11月10日


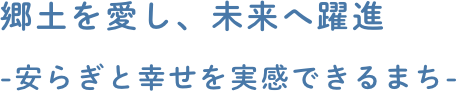
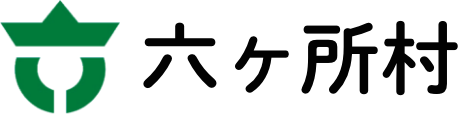
 印刷
印刷


 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭