国民健康保険税
1.国民健康保険制度とは
国民健康保険制度は、病気や怪我をしたとき経済的な心配がなく安心して医療が受けられるよう加入者全体で
国民健康保険税を出し合い健康と暮らしを守る助け合いの制度です。
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいた国民健康保険税と国などの負担金で成り立って
います。その財源をもとに医療費やその他さまざまな給付を補っています。
そのためみなさんの納める国民健康保険税は、大切な国民健康保険の財源となります。
2.納税義務者について
国民健康保険税は、1世帯当たりごとに世帯主の方の名前で課税されます。
世帯主の方が国民健康保険加入者でない場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合は、
世帯主の方の名前で課税されます。
※世帯主の方が国民健康保険加入者でない場合は、国民健康保険税の課税計算には含まれません。
国民健康保険税は年度ごと(4月から翌年3月まで)で計算されます。
年度途中で国民健康保険に加入した場合や脱退した場合の国民健康保険税は、月割で計算することとなります。
加入の届出をした日からではなく、国民健康保険の加入資格を得た時点で計算されるので、届出が遅れると
遡って国民健康保険税を納める場合があります。
国民健康保険を脱退する届出についても、届出が遅れると国民健康保険税と他の医療保険制度の保険料を
二重に納付する場合もあるため、加入や脱退の届出は書類が届き次第、14日以内に行うこと必要があります。
3.国民健康保険税の計算について
国民健康保険税は次の表のとおり、3つの課税区分に分けられ、それぞれ4つの計算項目があります。
それぞれの項目の税率に世帯の状況を当てはめて計算し、すべての金額を合計したものを国民健康
保険税として課税しています。(課税限度額を超えて課税されることはありません。)
令和7年度
| 算出基礎となる項目 | 基礎課税分 | 後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分※ | |
| 対象となる年齢 | 0歳~74歳 | 0歳~74歳 | 40歳~64歳 | |
| 所得割 | 基礎控除額後の 総所得金額 |
総所得金額×7.60% | 総所得金額×2.70% | 総所得金額×2.30% |
| 均等割 | 世帯の国民健康保険 加入人数 |
加入人数×33,000円 | 加入人数×9,600円 | 加入人数×9,000円 |
| 平等割 | 1世帯あたり | 23,000円/1世帯 | 8,000円/1世帯 | 6,500円/1世帯 |
| 課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | |
〇六ヶ所村に転入して国民健康保険に加入した方に対する国民健康保険税について
税額の計算に必要な所得を前住所地等の市町村に照会をする必要があるため、最初に所得割を除いた項目の分で税金を
納めていただき、所得確認後に所得割分を追加で納めていただくことがあります。
※介護納付金分とは?
寝たきりや認知症等になり介護が必要になった場合、適切な介護サービスが受けられるよう40歳から64歳までの方が加入
されている健康保険で保険料を納め、介護を社会全体で支えていくためのものです。
平成12年4月から国民健康保険や社会保険などすべての健康保険に導入されています。
納付方法は、40歳の誕生月のある月(1日が誕生日の場合はその前月)の分から介護納付金が加算され、その合計額
を国民健康保険税として納付していただきます。
国民健康保険税の計算例
世帯モデル(国民健康に加入する4人家族の場合)
| 国民健康保険 加入者の年齢 |
前年の 給与収入 |
前年度の 合計所得金額 |
国民健康税 基礎控除額 |
|
| 世帯主 | 41歳 | 3,500,000円 | 2,370,000円 | 430,000円 |
| 妻 | 38歳 | 1,200,000円 | 650,000円 | 430,000円 |
| 子 | 15歳 | 収入なし | 所得なし | なし |
| 子 | 5歳 | 収入なし | 所得なし | なし |
課税標準額の計算
課税所得額 = 合計所得金額 - 国民健康保険税基礎控除額
| 合計所得金額 | 国民健康税 基礎控除額 |
課税所得額 | |
| 世帯主 | 2,370,000円 | 430,000円 | 1,940,000円 |
| 妻 | 650,000円 | 430,000円 | 220,000円 |
| 世帯全体の課税所得額 (世帯主と妻の合計) |
2,160,000円 | ||
世帯の国民健康保険税額
|
算出基礎
となる項目
|
基礎課税分 | 介護納付金分 (世帯主のみ課税) |
後期高齢者 支援金分 |
合計金額 |
| 対象の年齢 | 0~74歳 | 40~64歳 | 0~74歳 | |
| 所得割 | 2,160,000円×7.60% =164,160円 |
1,940,000円×2.30% =44,620円 |
2,160,000円×2.70% =58,320円 |
267,100円 |
| 均等割 | 4人×33,000円 =132,000円 |
1人×9,000円 =9,000円 |
3人×9,600円=28,800円 1人×4,800円=4,800円(未就学児) |
174,600円 |
| 平等割 | 23,000円 | 6,500円 | 8,000円 | 37,500円 |
| 合計 | 319,160円 | 60,120円 | 99,920円 | 479,200円 |
最初の計算時点での本世帯例の国民健康保険税額は479,200円/年となります。
ここから世帯の所得が軽減判定基準以下※である場合に軽減が受けられます。
所得の低い世帯は、世帯の合計所得に応じて下表のとおり均等割と平等割が軽減されます。
軽減判定については、世帯主が国民健康保険加入者で無い場合も軽減判定にふくみますが課税算定には含みません。
軽減割合
| 軽減割合 | 前年中の所得 |
| 7割 | 43万円+10万円×(給与・年金所得者の合計数-1) |
| 5割 | 43万円+(30万5千円×国保加入者※)+10万円×(給与・年金所得者の合計数-1) |
| 2割 | 43万円+(56万円×国保加入者※)+10万円×(給与・年金所得者の合計数-1) |
※国民健康保険加入者数には、特定同一世帯所属者は含みません。
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し同一の世帯に属する方を意味します。
また、擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は国民健康保険加入者数に含みません。
この世帯例(世帯全体の課税所得額2,160,000円)の場合は、以下のとおりとなります。
| 軽減割合 | 計算式 | 軽減判定 基準額 |
世帯全体の 課税所得額 |
| 7割 | 43万円+10万円×(2人-1) | 53万円 | 216万円 |
| 5割 | 43万円+(30万5千円×4人)+10万円×(2人-1) | 175万円 | 216万円 |
| 2割 | 43万円+(56万円×4人)+10万円×(2人-1) | 277万円 | 216万円 |
世帯全体の課税所得額が軽減割合の基準額より低いところが該当する軽減割合となります。
この世帯例の場合、軽減判定基準額>世帯全体の課税所得額となるのは2割です。
したがって、この世帯例に適用する軽減割合は2割となります。
国民健康保険税額に軽減がある場合(2割軽減)
| 軽減項目 | 軽減摘要前の金額 | 軽減割合 | 軽減適用後 |
| 所得割 | 267,100円 | 摘要なし | 267,100円 |
| 均等割 | 174,600円 | 2割 | 139,600円 |
| 平等割 | 37,500円 | 2割 | 30,000円 |
| 合計 | 479,200円 | - | 436,700円 |
2割軽減適用後の国民健康保険年税額は、479,200円から436,700円(42,500円の減)となります。
なお、軽減割合の計算時、合計金額ごとに100円未満は切り捨てにしています。
(注)軽減の制度については5.軽減についてを参照ください。
4.税金の納め方について
国民健康保険税の納付方法は、以下の3つがあります。
年度途中に加入された方や遅れて加入の届出をした方については、納期限の都合で納めていただく回数が変わることが
あります。社会保険等に加入して税額が変更となった時、変更後の額と既に納めた額を比べて納めた額の方が多かった
場合は還付します。このことにより本来の税額よりも納め過ぎになることはありません。
| 名称 | 納付方法 | 納付回数 |
| 普通 徴収 |
納税通知書を使って金融機関で納める方法。 六ヶ所村役場及び各出張所、指定金融機関及び取扱金融機関等で納付が可能です。 指定金融機関及び取扱金融機関等については、納税通知書内に記載しています。 |
8回 |
| 口座 振替 |
納期限の日に税金を自動的に口座から引き落としする方法。(平成29年度より開始) 口座から引き落としをするためには届出が必要です。 詳しくはホームページ内の口座振替についてのページをご覧ください。 |
8回 |
| 特別 徴収 |
次の要件を満たしていると自動的に切り替えとなります。 ①世帯主が国民健康保険の加入者であること ②世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満であること ③世帯主が年額18万以上の年金受給者であること ④世帯主が介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国民健康保険税の合算額が 年金受給額の2分の1を超えていないこと 以上の①~④までの要件に1つでも該当しない場合は、普通徴収となります。 また、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行する方がいる世帯については、 移行する年度は普通徴収になります。 ただし、条件にあてはまっていれば、翌年度から特別徴収に戻ります。 |
6回 |
世帯構成別による特別徴収事例
| 事例 | 世帯主の年齢 加入保険種類 |
妻の年齢 加入保険種類 |
子等の年齢 | 徴収方法 |
| 1 | 72歳 (国民健康保険世帯主) |
68歳 (国民健康保険) |
- | 特別 徴収 |
| 2 | 72歳 (国民健康保険世帯主) |
68歳 (国民健康保険) |
- | 普通 徴収 |
| 3 | 78歳 (後期高齢者医療保険、擬制世帯主) |
68歳 (国民健康保険) |
- | |
| 4 | 72歳 (社会保険、擬制世帯主) |
68歳 (国民健康保険) |
- | |
| 5 | 72歳 (国民健康保険世帯主) |
68歳 (国民健康保険) |
40歳 (国民健康保険) |
|
| 6 | 72歳 (国民健康保険世帯主) |
68歳 (国民健康保険) |
40歳 (社会保険) |
特別 徴収 |
※擬制世帯主とは、国民健康保険制度に加入していない世帯主を指します。
特別徴収される税額の徴収方法
国民健康保険税額は、7月に決定することから、徴収額の1回当たりの負担を軽減するために、
税額が確定していない4月・6月・8月は仮徴収をし、税額確定後の10月・12月・翌年2月を
本徴収として徴収しております。
| 年金支給月 | 徴収区分 | 納付方法 |
| 4月 | 仮徴収 |
前年度2月に特別徴収された税額で徴収。 |
| 6月 | ||
| 8月 | ||
| 10月 | 本徴収 |
本年度の国民健康保険税額から仮徴収の合計額を差し引いて、 |
| 12月 | ||
| 翌年2月 |
特別徴収から口座振替への変更
原則として、特別徴収の条件を満たす方については特別徴収による納付となります。
条件を満たす方については申請により、口座振替による国民健康保険税の納付に変更することができます。
口座振替への変更条件は、口座振替による納付が確実にできること。現在、国民健康保険税の滞納がない方が対象となります。
【手続き方法】
①口座振替の手続き
手続の詳細は、ホームページ内の口座振替についてのページをご覧ください。
現在口座振替をご利用されている方は口座振替依頼手続きは不要です。
②納付方法変更の手続き
納付方法変更申出書を記載の上、提出してください。
手続きに必要な書類等
・納付方法変更申出書
・口座振替依頼書のお客様控え(控えがない場合はご相談ください)
・資格確認書、または資格情報のお知らせ
【注意事項】
・特別徴収を希望される方は、手続きの必要はありません。
・申請後、特別徴収が停止するまで約3~4か月程必要です。
・納付方法の違いにより納めていただく総額は変わりません。
・残高不足等で口座振替が不能となった場合は、納付書で納めていただきます。
また、翌年度以降からは特別徴収に戻る場合はあります。
・現在、納税貯蓄組合に加入されている方はご利用できません。
5.軽減について
国民健康保険税の軽減制度には以下の①~⑦があります。
①低所得世帯に対する軽減制度
所得の低い世帯は、世帯の合計所得に応じて、次の表のとおり均等割及び平等割が軽減されます。
未申告の方は、所得の軽減を受けられませんので、必ず申告をしましょう。
②未就学児の軽減制度
未就学児(6歳に達する年の3月31日まで)の均等割額が半額に減額されます。
また、上記①の軽減制度が適用されている世帯では、その金額のさらに半額が軽減されます。
③後期高齢者医療制度に移行される方
国民健康保険制度から後期高齢者医療保険制度に移行し、世帯内の国民健康保険に加入している人の数が
1人になる場合は、75歳の誕生日を迎えて国民健康保険を脱退した時点から基礎課税分と後期高齢者支援
金分の平等割を5年間半額にして税金を計算します。
軽減は75歳到達時点の世帯状況で判定するため年度途中で該当になる場合もあります。
5年間の軽減が終了したあと3年間は、平等割を4分の3にして計算します。
世帯の変更があった場合は、その時点で軽減の対象外となります。
④社会保険などの扶養になっていた方(旧被扶養者軽減)
社会保険の加入者だった方が後期高齢者医療保険制度に移行することにより、社会保険の扶養となっていた人が、
国民健康保険に加入する場合があります。その加入された方で65歳以上の方は、後期高齢者医療保険制度に
移行するまで所得割を0円、資格の属する月以後の2年間の均等割を半額にして税額の計算をします。
必ず申請が必要になりますので、忘れずに届出をするようにして下さい。
⑤非自発的失業者
倒産・解雇等の理由で離職し、雇用保険特定受給者となった65歳未満の人は、国民健康保険税の算定に必要な
給与所得を3割にして税額を計算します。軽減の期間は、退職日の翌日から翌年度末までの間です。
雇用保険受給資格者証の離職理由が次の表の番号に該当となる方は、申請により対象となります。
| 特定受給資格者に対する 離職コード |
離職理由 |
| 11 | 解雇 |
| 12 | 天災などによる事業継続不可のための解雇 |
| 21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知有り) |
| 22 | 雇止め(雇用期間3年未満雇止め通知有り) |
| 31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由有りの自己都合退職 |
| 32 | 事業所移転等に伴う正当な理由ありの自己都合退職 |
| 特定理由離職者に対する 離職コード |
離職理由 |
| 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示無し) |
| 33 | 正当な理由有りの自己都合退職 |
| 34 | 正当な理由有りの自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
⑥特定の介護施設に入所されている方
40歳から65歳未満の介護納付金分が課税されている方で、指定障害者支援施設の対象となっている施設に入所
されている方は、申請していただくことによって介護給付費分が課税されません。
施設に入所したときや退所したときは、忘れずに申請を行うようにしましょう。
⑦産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度(令和5年度より開始)
国民健康保険の被保険者で、出産予定の妊婦の方は申請をいただくことによって保険税の所得割額と均等割額から、
出産(予定)月の前月から4か月相当分が減額されます。
出産後でも申請可能ですので詳しくは税務課までお問い合わせください。


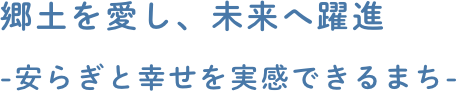
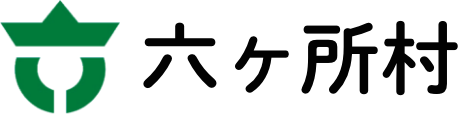
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭