後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
75歳以上の方が加入する医療保険で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から移ります。
また、65歳から74歳までの方で一定の障害がある場合は、申請により加入することができます。
運営は県内の40市町村全てが加入する「青森県後期高齢者医療広域連合」が主体となり、保険料の決定や医療を受けたときの給付などを行います。
市町村では、後期高齢者医療資格確認書の引き渡しや保険料の徴収、各種申請・届け出等の受付などを行います。
*青森県後期高齢者医療広域連合(ホームページ)http://www.aomori-kouikirengou.jp/
被保険者
▸ 75歳以上の方
▸ 65歳以上75歳未満で一定の障がいがあると認定された方(申請により加入することができます)
障がい認定の基準
▸ 身体障がい者手帳…1級、2級、3級、4級は障害等一部
▸ 療育(愛護)手帳…A(重度)
▸ 国民年金などの障がい年金…1級、2級
▸ 精神障がい者保健福祉手帳…1級、2級
※上記のいずれかに該当する方は、市町村窓口で申請すると広域連合の認定を受けた日から後期高齢者医療の被保険者となり、「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。
※75歳未満で一度加入した方でも、申請することにより後期高齢者医療の被保険者資格を喪失することができます。その場合、国民健康保険または被用者保険(健康保険組合や共済組合など)に加入することになります。また、一度喪失した方でも申請により再度加入することが可能です。
マイナ保険証・資格確認書
後期高齢者医療被保険者証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
詳細は、以下をご覧ください。
▸ マイナンバーカードの保険証利用について
▸ 厚生労働省のホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
令和8年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、1人に1枚、「後期高齢者医療資格確認書」が交付されます。資格確認書はハガキ型で、従来の被保険者証と同じように使用できます。
令和7年8月1日以降、医療機関等を受診する際はマイナ保険証又は資格確認書にて受付してください。
令和7年8月年次更新(有効期限:令和8年7月31日)の資格確認書については、7月中に送付します。
お手元に届いたら、記載内容をご確認ください。
<イメージ>後期高齢者医療資格確認書

【注意事項】
▸ 破損や紛失等の場合は、健康課にて再発行の申請をしてください。
▸ 死亡、転出などで資格喪失された場合は、健康課や村内各出張所へご返却ください。
医療費の自己負担割合
医療機関等での自己負担割合は、後期高齢者医療保険被保険者本人や、同じ世帯の方の前年の所得により、1割、2割、3割のいずれかになります。
自己負担割合は、前年の所得から判断し、8月1日から適用します。判定基準については、以下の表をご確認ください。
| 所得区分 | 負担割合 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ | 3割 | 住民税課税所得690万円以上 |
| 現役並み所得Ⅱ | 3割 | 住民税課税所得380万円以上 |
| 現役並み所得Ⅰ | 3割 |
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度被保険者がいる方 |
| 一般Ⅱ | 2割 | 住民税課税所得が28万円以上※2 |
| 一般Ⅰ | 1割 | 現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般Ⅱ、低所得者Ⅰ・Ⅱに当てはまらない方 |
| 低所得者Ⅱ | 1割 | 住民税非課税世帯で低所得者Ⅰ以外の方など |
| 低所得者Ⅰ | 1割 |
住民税非課税世帯で |
※1 3割負担が1割または2割負担に変更となる場合
・被保険者本人の前年の収入額が383万円未満の場合
・同じ世帯の被保険者全員の前年の収入の合計が520万円未満の場合
・同じ世帯に70歳以上75歳未満の他の医療保険に加入している者がいる場合、被保険者本人と70歳以上75歳未満の方全員の前年の所得が520万円未満の場合
※2 世帯内の後期高齢者のうち、課税所得が28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上(単独世帯の場合。複数世帯の場合は、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上)の対象者
保険料
令和7年度の保険料
▸ 青森県後期高齢者医療広域連合で定められている保険料率をもとに、被保険者1人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
保険料の算出方法は下記のとおりです。
[ 均等割額 ] [ 所得割額 ] [ 保険料額 ]
(被保険者全員が納める額) + (所得に応じて納める額) = 80万円が上限
46,800円 基礎控除後の所得※×9.90%
保険料の軽減措置(令和7年度も継続して実施)
▸ 所得が少ない方
被保険者とその世帯の世帯主の所得を合わせた合計所得に応じ、均等割額が7割、5割、2割軽減されます。
| 世帯の所得額の合計 | 軽減割合 |
|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数ー1)以下 | 7割 (32,760円) |
| 43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円(年金・給与所得者等の数ー1)以下 | 5割 (23,400円) |
| 43万円+(56万5千円×被保検者数)+10万円(年金・給与所得者等の数ー1)以下 | 2割 (9,360円) |
▸ 後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険※ の被扶養者であった方
後期高齢に加入してから2年間は、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担がありません。
※ 被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合などです。
保険料の納付方法
▸ 特別徴収(年金額が18万円以上の方で、介護保険料と合わせた保険料が1回あたりの年金受給額の2分の1を超えない場合)
…年金から天引き
▸ 普通徴収 (年金額が18万円未満の場合や、年金額が18万円以上の方でも、介護保険料と合わせた保険料が1回あたりの年金受給額の2分の1を超える場合)
…納付書による納付※1または、口座振替による納付※2
※1 納付については、取扱金融機関のほか、役場または各出張所でも納付できます。
≪取扱金融機関≫ 青森みちのく銀行、青森信用組合(六ヶ所支店のみ)、ゆうき青森農業協同組合
預金口座振替依頼書は、健康課または、村内の取扱金融機関にあります。
保険料の納付相談
後期高齢者医療保険料の納付が著しく困難な方のために、納付相談を実施しております。お気軽にお問合せください。
その他の申請
高額療養費について
1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が上限額を超えた場合は、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
詳細は、こちら![]() 高額療養費についてをご覧ください。
高額療養費についてをご覧ください。
次の必要書類をご用意のうえ申請(健康課または出張所)をお願いいたします
※被保険者本人以外に振り込む場合、別途、委任状【記入例】と印鑑(申請者と代理人それぞれのもの)が必要になります。
・高額療養費支給申請書【記入例】
・通帳
・マイナンバーカード(通知カード等マイナンバーがわかるもの)
・身分証明書
高額介護合算療養費について
医療費が高額になった世帯に介護保険者の受給者がいる場合、医療保険と介護の両方の自己負担額を年間で合算し、所得区分に応じた限度額を超えた金額が支給されます。
詳細は、こちら![]()
![]() 高額介護合算療養費についてをご覧ください。
高額介護合算療養費についてをご覧ください。
次の必要書類をご用意のうえ申請(健康課または出張所)をお願いいたします
※被保険者本人以外に振り込む場合、別途、委任状①【記入例】と印鑑(申請者と代理人それぞれのもの)が必要になり、重度心身障がい者医療費助成受給者用は、別途、委任状②【記入例】と印鑑が必要になります。
・高額介護合算療養費等支給申請書【記入例】
・通帳
・マイナンバーカード(通知カード等マイナンバーがわかるもの)
・身分証明書
療養費について
以下のような場合、医療費の全額を本人がいったん支払いますが、申請(支払った日から2年以内)により自己負担額を除いた金額が給付されます。
● 医師の指示により、治療用装具(コルセット・関節用装具・)を購入されたとき
● 医師の指示により、はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
● 海外で治療を受けたときや、旅行中の急病などでやむを得ず保険証を提示できず診療を受けたとき
次の必要書類をご用意のうえ申請(健康課または出張所)をお願いいたします
※被保険者本人以外に振り込む場合、別途、委任状【記入例】と印鑑(申請者と代理人それぞれのもの)が必要になります。
・療養費支給申請書【記入例】
・通帳
・マイナンバーカード(通知カード等マイナンバーがわかるもの)
・身分証明書
受領申立書について
被保険者が亡くなった場合、生前に負担した医療費の支給(高額療養費)等が発生した際に、被保険者本人に代わり受領していただく方(相続人)の確認、および給付に関する帳票等の送付先を申請者宛に変更させていただく書類です。
次の必要書類をご用意のうえ申請(健康課または出張所)をお願いいたします
※申請者(相続権のある方)以外に振り込む場合、別途、委任状【記入例】と印鑑(申請者と代理人それぞれのもの)が必要にます。
・ 受領申立書【記入例】
・通帳
・マイナンバーカード(通知カード等マイナンバーがわかるもの)
・身分証明書
葬祭費について
被保険者が亡くなった場合、申請(葬儀を行った翌日から2年以内)をすることで葬儀を行った方に50,000円が支給されます。
次の必要書類をご用意のうえ申請をお願いいたします
※喪主の方以外に振り込む場合、別途、委任状【記入例】と印鑑(申請者と代理人それぞれのもの)、身分証明書が必要になります。
・葬祭費支給申請書【記入例】
・喪主の方の通帳
・会葬礼状または、葬儀費用の領収書の写し(喪主または費用負担者の名前(フルネーム)が確認できるもの)
詳細は青森県後期高齢者医療広域連合のホームページからもご覧いただけます。
*青森県後期高齢者医療広域連合(ホームページ)http://www.aomori-kouikirengou.jp/


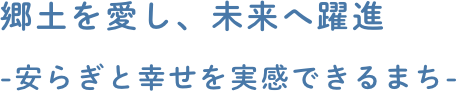
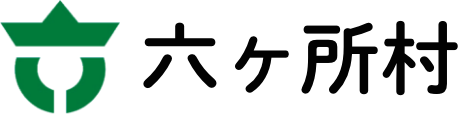
 印刷
印刷
 戻る
戻る
 ページの先頭
ページの先頭